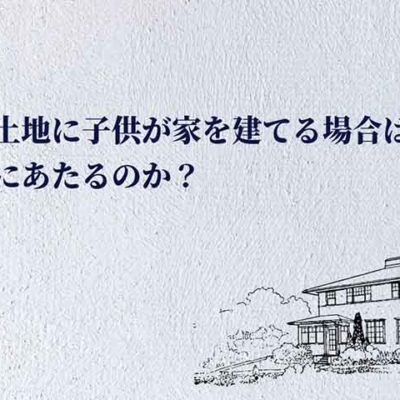後継者不足が深刻化
高齢社会、人口減少、日本経済が減速し続けるなか、長年、日本を支えてきた個人事業、零細企業、中小企業の多くで、経営者の引退が急速に増加しています。
完全に廃業する道もありますが、従業員や、今まで取引してきた顧客や取引先のことを考えると、簡単に廃業をすることはできません。
誰かに跡を継いでもらいたい、そう悩んでいる経営者がたくさんいます。
中小企業のM&A市場が急成長
注目を浴びているのが、後継者を外部にもとめる、M&Aです。
以前は、M&Aと言えば大企業だけの話でした。現在は、中小企業のM&A市場が急速に成長しています。
経営者としては、苦労して育て守ってきた会社が残り、従業員や取引先も守られる、とても良い方法に思えます。
しかし、ここ数年、M&Aによるトラブルが激増しています。
これからM&Aによる事業承継を検討される経営者のみなさんは、本当に信頼できる相手かどうか、慎重に見極める能力が問われます。
M&Aトラブル
中小企業のM&Aトラブルでトラブルが激増しています。ニュースや新聞の記事で取り上げられることが多くなったので、ご存じの方も多いかと思います。
トラブルの大半がM&Aで企業を買った側の問題です。
中小企業庁もM&Aトラブルに対して注意喚起をしています。
中小企業庁HP(『M&Aに関するトラブルにご注意ください』)
特に注意してほしいケースとして以下の2つの例があげられています。
- クロージング後、個人保証が解除されなかった事例
- 譲渡対価の分割払い、退職慰労金の後払いが株式譲渡契約の条件となっているものの、履行されなかった事例
元の経営者からM&Aで事業を承継する際、いくつかの要望、約束が取り交わされますが、それを反故にして、やりたい放題した結果、会社を潰してしまうケースが多発しています。
このようなトラブルでは、M&Aで企業を買う側に、もとから事業承継の意思はなく、別のねらいがあります。
M&Aトラブル 買収側の3つのねらいとは?
一般的には、M&Aでは、事業承継、つまりビジネスそのものを継続することを前提条件に買収します。
事業を継続することで、利益、キャッシュフローや、その事業のシェアを獲得することができます。
企業を買収する側からすると、その事業分野での成功に要する時間を短縮することが可能となります。
収益のあるビジネスと時間を買うことができ、M&Aによって大きな効果が得られます。
一方で、純粋にビジネスを買うのではなく、その企業の資産をねらうM&Aも多々あります。安く買って高く売る、資産の転売や、資産そのものがねらいのケースです。
M&Aトラブルになるケースは、このケースが大半を占めていると思われます。
誰だって自分の持っていた物を売った先が、自分から買った金額より高く転売して利益を上げるのを見るのは嫌なものです。
ましてや、長年育ててきた会社を、事業継続の約束を反故にして、従業員を解雇し、資産をバラバラにして売り捌かれるのは腹が立ちます。
M&Aのねらいとなる資産は、おもに3つあります。
以下の資産を手に入れたら会社や事業は不要なので廃業したり倒産させたりするトラブルが発生します。
キャッシュ(現預金等)
一つ目は、潤沢なキャッシュ(現預金)です。
古くから安定的な経営を続けてきた中小企業の中には、多額のキャッシュを持つ企業があります。まじめな経営者ほど、事業を継続していくうえで、何かあったときに対応できるようにキャッシュを積み上げています。
数年前のコロナ禍や大規模災害時のように、予想できない事態が起こっても、事業と従業員を守るために積み上げてきたキャッシュがねらわれます。
M&Aが成立するまでは、元の経営者に良い顔をしていますが、ひとたび会社を買ったあとは、即座にそのキャッシュが使われたり、抜かれたりします。
最近では家電メーカーの船井電機がこのケースに似ています。
潤沢な資金があったはずが、M&A後に資金が流出し、船井電機は破産、従業員は即刻解雇になりました。
不動産
二つ目は、不動産です。
歴史のある企業で、工場などの土地を所有している企業がねらわれます。事業継続には必須である工場などの不動産を、M&A後に事業をやめて売却してしまうのです。当然、従業員は解雇されます。
歴史がある企業は、土地を購入した時期が数十年前、不動産価格の安い時代に取得しているので、簿価が安く、多くの含み益、資産を持っています。
もとからこの含み資産をねらってM&Aにより企業を買収したのであれば、早々に不動産を売却し、利益を確定してしまうことでしょう。
経営者が事業の継続を望んでいるのに、買主側が事業を廃業し不動産を売る意図を隠して取引を成立させるとトラブルになります。
買主候補が不動産ねらいのM&Aであることを表明して売主の経営者が納得していれば問題にはなりません。
不動産M&A
会社に価値のある不動産がたくさんある場合には、事業と不動産を分けた方が高く売れることがあります。
経営者は、事業を継続する会社と不動産だけを所有する会社に分割し、別々に売却する方法を選択することができます。
不動産だけを所有する会社の取引は不動産M&Aと言われます。
私が以前勤めていた不動産会社でも、不動産M&Aを積極的に行っていました。
その多くは買主側で、不動産の仕入れのために会社ごと買っていました。
売主側のコンサルタントが、事業を承継する会社を別に作っていて、売りに出す元の会社は不動産のみを所有する会社にしてくれていました。
不動産の時価と、不動産投資としての収益で評価すればよいので、不動産会社としては価格をつけやすかったです。
一番大きかった取引は、200億円近かったと記憶していますが、私がいた会社は買ったのち、わずか半年で不動産を売却し、数十億の利益を得ました。
私は当時、不動産の精査や売買取引の雑多な業務、バックオフィスを担当しました。
一つの不動産には、管理運営に関する複数の雑多な契約、鍵や設計図書などのたくさんの付属物があります。
それをいっぺんに数十物件買うことになるので、取引時にはすべてチェックしなければなりません。
とにかく時間と手間がかかって大変でした。
不動産M&Aは、売る側も買う側も時間と人が必要です。
知的財産権
三つ目は、知的財産権です。
知的財産権とは、特許権や著作権など、知的な活動で産まれた財産的な価値のあるものを指します。企業のM&Aでは、知的財産権のうち、主に特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ、産業財産権と言われている権利が関係してきます。
中小企業のなかには、価値のある知的財産権を保有している企業がたくさんあります。その価値を経営者が正しく評価していない場合もあります。M&Aにおいては、眠っていて活用されていない知的財産権を目的にする企業もあります。
経営者が自社の持つ知的財産権の価値を正しく評価し把握していなければ、かなりの安い買い物となる可能性があります。
このような場合、知的財産権さえもらえれば、その企業の事業そのものは不要になり、M&Aで経営権を得たらすぐに廃業してしまうこともあり得ます。
M&Aで失敗しないために必要なこと
自社の資産価値を正確に把握する
M&Aで失敗し、後悔しないためには、自社の持つ資産を把握し、その価値を正しく評価しなければなりません。
会計帳簿である程度わかるのですが、その評価が正しいかどうか、その点は慎重に吟味すべきです。
一番頼りになるのは、長年のパートナーと言える税理士や会計士になります。中には申告業務に特化しており、コンサルティングが苦手な税理士もいますが、会社の資産について、彼らの意見は参考になるはずです。
不動産については、帳簿の評価(簿価)では判断できません。大事なのは時価です。不動産価格は上昇しているので、簿価よりも時価の方がかなり高くなっています。売ったらいくらになるか、時価に注目して資産を評価しなければなりません。不動産の価値については、懇意にしている不動産業者など、不動産分野のプロに相談する必要があります。
不動産はその用途によって価値が変わります。
工場として利用するよりは、タワーマンションを建てた方が土地の時価は上がります。
上に伸ばして延べ面積を増やすことができる土地であれば時価は上がりやすくなります。
そういう土地を多く持つ企業は狙われやすいと言えます。
仲介者は必ずしも味方ではない
後継者を外部に求めることは悪いことではありません。しかし、そのためにはM&Aを仲介する者の存在が欠かせません。仲介者としては、銀行、M&A仲介会社などがあげられます。
しかし、仲介者は経営者にとって必ずしも味方ではありません。
経営者は重要な相談相手である仲介者の意見を鵜呑みにできないのです。
仲介者の目的は成立時に受け取る成功報酬です。
何としても見つけてきた買主候補で取引を成立させなくてはなりません。
買主候補を見つけるのは困難であり、検討に時間も費用もかかります。
そう何組も検討させるほど待てません。
仲介者は、買主側の条件を売主側にできるだけ飲ませ、譲歩させて取引をまとめようとする傾向があります。
この点は、不動産売買の仲介業者も似ています。
さいごに
経営者は、自らの引退の時期をできるだけ早く決めなければなりません。
後継者がいない場合、後継者を探すためにかなりの時間が必要だからです。
廃業する場合も同じです。
顧客、取引先、従業員の理解を得るため丁寧に説明し時間をかけるべきです。
M&Aには準備のために多くの時間が必要です。
急ぐあまりに仲介者など他社に頼り、人任せで決めてしまうようでは納得のいくM&Aにはなりません。
経営者には、自らの引退の為に、事前準備に十分な時間をかけた綿密なプラン作りが求められます。